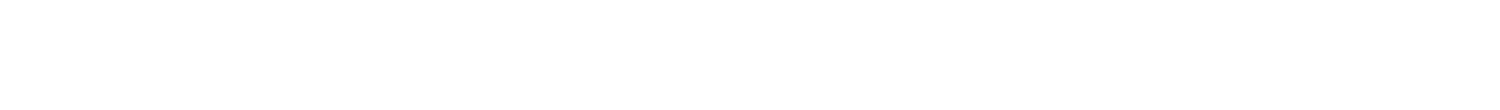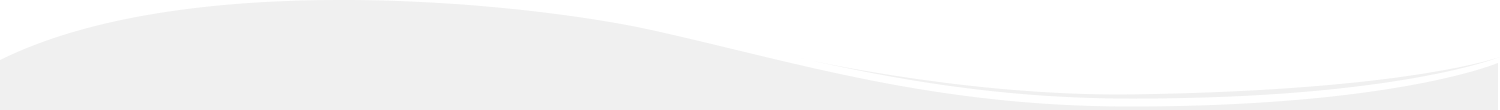仕事をするなら、社会の困りごとに役立つ仕事がいい。
仕事をするなら、社会の困りごとに役立つ仕事がいい。
大学で経済学を学ぶ中で、労働人材不足について知りました。今後どんな仕事をしていこうかと考えた時に、なにか社会が困っていることにアプローチしたいという考えがあったので、それなら人材関連だろうと思ったのです。
医療分野を選んだのは、高齢化問題などもあってこれからは医療や介護分野での人材不足がますます深刻になるだろうと。それに、自分の祖母が施設に通っていて、医療の現場のたいへんさを身近に感じていたことも、理由のひとつだったかもしれません。
実際に営業として接してみると、職種や業務内容など知らなかったこともたくさんあるし、専門知識も必要です。先輩に同行しながらメモをとって後でわからないことを聞いたり、自分で調べたりして日々勉強しています。月1回のWEB研修などもあるので、それも役に立っています。

営業でも人材コーディネーターの役割もあり、幅広く経験を積むことができます。
営業でも人材コーディネーターの役割もあり、幅広く経験を積むことができます。
仕事は新規開拓が第一ですが、人材コーディネーターとしての役割も兼ねています。既存の取引先とも良好な信頼関係を築いていかなければいけないし、派遣するスタッフの面接や労務管理、メンタルケアも大事な仕事です。いろいろあってバランスが難しいといえば難しい。
でも一方で、ひとつの仕事の中でいろいろな経験を積めるのはよいところだと思っています。たとえば、現場で働くスタッフの不満や悩み事の相談に乗ったりすることもありますが、現場の実情に詳しいということが次の営業の役に立ったり、信頼につながったりもします。ひとつひとつの仕事が相互につながっているのです。
仕事はたいへんですが、確実にメンタル強くなりますね。アポイントが取れたとか取れないとか一喜一憂しない。むしろ訪問の機会をいただけたときは「ありがとう」って思います。

“第二の採用担当者”という気持ちが信頼を築く上で大事。
“第二の採用担当者”という気持ちが信頼を築く上で大事。
仕事をする上で大切にしていることは、いい意味で“期待しすぎない”こと。人材派遣は、あくまでお客さまが困っている時にサポートするのが仕事です。
以前、自分が新規開拓した病院で、4ヶ月通ってようやく受注をいただいたことがありました。ところが、それから1ヶ月程して、たまたま病院の方に正規雇用の応募者があり、派遣の話はキャンセルになってしまいました。それは残念なことかもしれませんが、でも、病院にとってみればいいことだということに気づいたのです。
受注を取る、ということを期待し過ぎると、それが見えなくなってしまいます。まず相手の立場に立つということ。私は、病院の第二の採用担当者という気持ちでいつも仕事をしています。それが、信頼につながり、結局は受注にもつながっていると思っています。